お弁当に入れるおかず、特に野菜のおかずは傷まないかな?と不安になりますよね。
夏場はもちろん、季節を問わずお弁当作りには食中毒対策は本当に気を使います。
- どんな野菜のおかずが傷まないのかな?
- 簡単で傷まない野菜のおかずの作り方は?
私も約30年家族のために毎日作っており、毎日2品野菜のおかずを作っています。
傷まない野菜のおかずを作るために、30年ずっと気をつけていたポイントは次の4つです。
- 野菜から出る水分をできるだけ飛ばす:水分が多いと食中毒の原因になります。
- 生野菜は避ける:冬場以外、ミニトマトを含めて生野菜は入れません。
- しっかり冷ましてからお弁当箱のフタをする:水分と同じくらい温度管理が大事です。
- 暑い季節は保冷剤を忘れない!:これが一番手っ取り早い確実な方法です。
このポイントに気をつけていれば、お弁当の野菜が傷んでしまうことはほぼ防げます。
この記事では、傷みにくいお弁当の野菜のおかずについて更に細かい情報と、簡単に野菜のおかずを作るアイデアも4つご紹介します。
\わさび成分の抗菌作用に期待して使ってます!/
お弁当に入れて傷まない野菜のおかず:水分を飛ばす
お弁当に入れる野菜のおかずは、とにかく水分を飛ばして少なくします。
- 生野菜
- 水分の多いままの煮物
- おひたしやあえ物
お弁当にサラダは大丈夫?生野菜をお弁当に入れるときの注意点
私個人は、生野菜は真冬以外お弁当に入れないようにしています。
でも、サラダを持って行きたい!ということもありますよね。
お弁当に生野菜を入れるときには、次のような工夫が食中毒対策に効果的です。
- ミニトマト:必ずヘタを取って洗い、よく水気を拭く。事故防止のためにも使わない方が無難。
- キュウリ:塩もみにしてギューっと水分をしぼったものを使う。または洗ってよくよく水分を拭き取って使う。
- レタス:基本的にNG。ごはんとおかずの仕切りに使うと見ためも味も悪い
- サラダを持って行きたい:サラダだけ別の器に入れて、ドレッシングやマヨネーズは別添えにする
ミニトマトは幼稚園のお弁当などによく入れがちだと思いますが、丸のまま飲み込んでしまい、窒息する事故も起きています。
出来れば家庭のごはんで使うか、運動会などで親の目が届くときにいろどりで使うと安心です。
キュウリについては、ちくわに詰めるのが定番だと思いますが、その時はキッチンタオルでしっかり水分を拭き取って使ってくださいね。
サラダをお弁当に持って行きたいときは、ドレッシングやマヨネーズは食べる直前に!
あらかじめかけてしまうと、野菜から水分がでて味も悪くなります。
野菜の煮物はできるだけ煮詰めるとよい
お弁当の定番、お野菜の煮物。私も毎日のようにお弁当に入れますが、これも傷まないようにするポイントがあります。
- 野菜の煮物:できるだけ煮汁を煮詰める
- 前日の夜に作って冷蔵庫で冷ましておく:煮物は冷めるときに味が染みるので美味しくなります。朝水分を切ってお弁当箱へ入れます
私は、野菜の煮物は前日の夜に夕飯のおかずと一緒に作り、小鉢に取り分けてラップをして冷蔵庫へ入れ、朝はそのままお弁当箱に詰めています。
味がよく染みるので、朝水分を切ってお弁当箱に入れても、ちゃんとお昼に美味しく食べられますよ。
和え物やおひたしは、おかかやおぼろ昆布、すりごまで水分を吸わせて
ホウレンソウのおひたしやブロッコリーのゆでたものも、お弁当の定番ですね。
- おひたしのお醤油やあえ物の味つけは前日の夜にして、朝は水分を切っておかかなどをまぶしてお弁当箱に詰める
- ブロッコリーはよく水分を振り切って入れる
アルミカップに入れて、ほかのおかずに味や水分は移らないようにするのも大切!
味を濃くすれば野菜のおかずは傷まないのでは?
よく、「味を濃いめにすると食中毒の予防になる」と言われますね。
でも。食中毒菌の繁殖を抑えることができるほどの濃さは、正直食べられないほどしょっぱくなります。
食中毒菌の繁殖が抑えられる塩分濃度は約10%。
腐敗を促す多くの微生物は、食品中の塩分濃度が5~10%になると増殖できなくなります。
しかしながら、塩分濃度10%未満の塩分控え目の食品は、腐敗菌を完全に抑えることができません。
常温で保存してしまうと、腐敗菌が増殖してしまう恐れがあります。
塩分濃度10%未満の食品は、冷蔵保存が必要なので覚えておきましょう。
塩分濃度10%の食品や調味料は、お醤油(そのまま)や伝統的な梅干し、塩辛などと同じ程度です。
塩分濃度0.8%:味噌汁などの汁物が美味しいと感じる濃度
1%:パスタのゆで汁
1.5%:お弁当の味付け:少し濃いめの味付けと感じる
3%:漬物:2週間保存可能
ー引用:東京新聞
このようなことから、「味付けを濃くすれば傷まない」というのはかなり無理がある、といえます。
お弁当の味を濃いめにするのは、食中毒対策ではなく、冷めても美味しく食べるため、と覚えておきましょう。
野菜のおかずが傷まないためには保冷剤が最強!
我が家では梅雨から夏にかけては保冷剤は必ず持たせます。
保冷剤を忘れたらお弁当食べるな、と家族に言い聞かせています。
お弁当が傷まないようにするためには、水分を少なくすることと、温度を下げることが最も効果的。
食中毒菌が活発になるのは、菌の種類によって幅あがありますが、おおむね35℃~50℃の温度です。
一般的に、食中毒菌は37℃前後でもっとも活発で、一方で65℃以上になると菌はほぼ死滅し、10℃以下では増殖が鈍ると言われています。
ー引用:ウエザーニュース
この温度になってしまう時間帯をできるだけ少なくするために、保冷剤がとっても有効です!
\保冷バッグにお弁当を入れたら更に安心です/
お弁当に入れて傷みにくい野菜のおかずのアイデア
お弁当に向いている野菜のおかずは、水分を極力飛ばした炒め物、揚げ物、濃いめの味付けで煮絡めた煮物などです。
- きんぴら風に炒め煮にする
- よく水気を切ったうえで、おかかやとろろ昆布を混ぜて水分を吸わせる
- アルミカップなどで小分けにして入れる
- ショウガや梅干し。お酢を使った味付けにする
夏以外の季節であれば、おひたしやナムル、ブロッコリーのゆでたものやポテトサラダ(きゅうりなど生野菜は入れない)も大丈夫です。
それでも水気はよく切って詰めましょう。水気があると、食中毒の原因になるだけではなく、汁漏れの原因にもなります。
おかずだけじゃない、炊いたご飯が傷まないようにするには?いつ炊けばいいの?という疑問には、こちらの記事でお答えしています。
ズボラでもできる!野菜の傷まないお弁当おかずの作り方
簡単にできて、傷みにくい野菜のおかずのアイデアを4つご紹介します。
改めて「お弁当のおかずを作ろう」と思うと面倒くさいものです。昨日の残りのアレンジや、ササっとできるようなものがいいですよね。
こんなのでいいの?というくらいズボラさんでもできるものを、4つご紹介します。
インゲンのおかか炒め
- インゲンの筋を取り、3~4等分に切る
- ライパンに油を少量しき、インゲンを入れて炒める
- 火が通ったらざっと醤油をまわしかけ、おかかを1パック入れて混ぜる
昨日の煮物の残りから揚げ
- 里芋やニンジンなどの野菜の煮物を夕飯のおかずにするとき、少し多めに作って残しておく。
- 翌朝、片栗粉をまぶしてサッと揚げる
もともと火は通っているので、表面が程よい色になったらOK。味もしみておいしいですし、水分も出ません。
昨日のおひたしの残りバターコーン炒め
- 夕飯で作った、ホウレンソウや小松菜など青菜のおひたしの残りを冷蔵庫で保存
- 翌朝、ライパンにサラダ油を少量入れて水分を飛ばすように炒める
- 冷凍コーンをそのまま適当に入れ、最後に香りづけのバターかマーガリンを少々入れる
- 塩か醤油で味を調える
最初にサラダ油を入れるのは、バターが焦げ付くのを防ぐためですので、最初からバターで炒めても大丈夫です。
昨日のとんかつに添えたキャベツの残りの梅干し和え
- 夕飯のキャベツの千切りが残ったら、ラップをして冷蔵庫で保存する。
- 翌朝、レンジでしんなりさせる(長時間レンチンすると焦げるので注意!)
- 粗熱が取れたらギューっと絞って水分を絞る
- 梅干しを叩いて細かくし、水気を切ったキャベツの千切りとお砂糖少々と混ぜる
キャベツの水気をきちんと絞らないと傷みやすくなりますので、しっかり絞りましょう。
朝、キャベツを切ってゆでても10分程度で作れます。
まとめ
- お弁当に入れて傷まない野菜のおかずは、水分の少ないもの
- 生野菜は極力さける
- 水分を極力飛ばした炒め物、揚げ物、濃いめの味付けで煮絡めた煮物などがお弁当に向いている
- 簡単にできて、傷みにくい野菜のおかずのアイデアをインゲンのおかか炒めなど4つご紹介
お弁当で傷みやすい野菜のおかずは水分の多いものです。おひたしやナムルなどはおかかやとろろ昆布などを活用して水分が出ないようにしましょう。
昨日のおかずの残りアレンジでも、傷まない野菜のおかずは作れます。
毎日のことですから、傷まないようにポイントはおさえて、上手に手抜きして作りましょう!
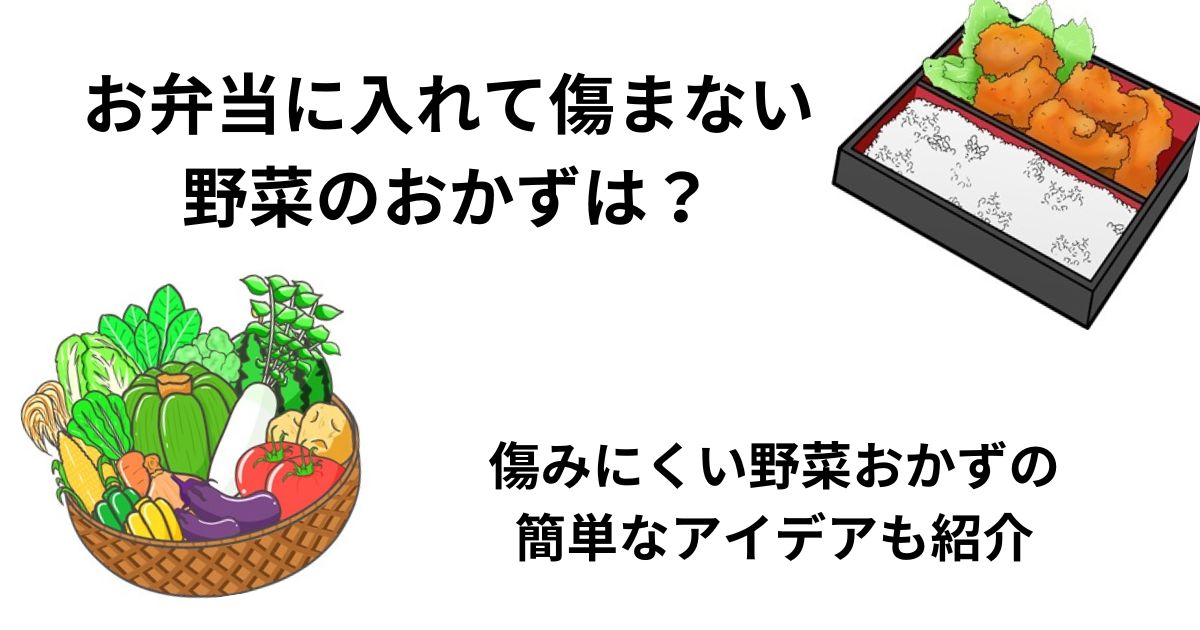





コメント